青木ヶ原の樹海から、南西の方角。
霊峰富士を望むとある岬に、一軒の小さな教会が建っている。
その夜は局地的な暴風雨が吹き荒れており、稲光が度々ステンドグラス越しに瞬いてい
た。さながら吸血鬼映画のワンシーンのように。
それもすべては森羅万象の理に逆らい、強引に世界の摂理を捻じ曲げる秘奥の業――
『開門術』を使用した影響であった。
単独で封滅結界を『渡る』ことが出来る最高位の術者二名が、二つの世界から同時に働
きかけることによって、隔絶された世界を一部分だけ繋ぐ禁断の秘術である。
木造の礼拝堂。磔にされた聖人の眼下にて、こたびの開門を果たした術者二人が対峙し
ていた。
「ようこそ我が教会へ、恭二さま。いいえ……獅条神父」
甘やかな声が、ずぶ濡れの黒衣に投げられた。声の主は修道女である。ヴェールで覆わ
れた素顔は美しい日本女性のものだ。若く見えるが老成した雰囲気を放っており、見た目
どおりの年齢と決め付けるのは些か憚られた。
祭壇に佇む彼女は存在しているだけで、周囲の空気を清浄なものに変えていく。人の手
によって模造された神像なぞよりも、彼女自身こそが御神体であるかのようだった。
夜分遅く教会を訪れた訪問者の装いは、十字架こそないものの確かに神父服じみている。
しかしその雰囲気たるや、神父というよりは吸血鬼……あるいは暗黒神官といった趣で
あろう。
「この私が神父、か。なるほど、それでは貴女のことはこう呼べばいいのだろうか。
シスター・ミナギ、と。……隠れ蓑に教会とはよくよく考えたものだ。まさか巫女が修
道女に扮しているとは誰も思うまい。尤も前御薙当主である貴女も、その姿で神楽を舞う
わけにはいかぬでしょうが」
シスターは片手を口に添えて、典雅に微笑んだ。
彼女は現役を引退した後も、こうして『外』に留まって、二世界を股にかけた言わば窓
口となっている。無論『外』に関わる面倒ごとは概ね彼女の仕事領分である。
「それで神父さま。今宵は如何様な御用向きでございましょうや?」
恭二は答えず、並ぶ机の一つに手を翳す。すると机の上に、浮遊する黒い球体が出現し
た。丁度人間一人分の大きさを持つ黒球は毛糸球のように解けていき、中から一人の少女
が出てきたのである。少女はゆっくりと浮力を失って、机の上に横たわった。
「あら、可愛らしい。ふふ、お子様ですか?」
「……私はまだそんな年ではないよ、シスター」
「それでは、今宵のお食事かしら? 私の前で不浄を行う勇気があるのなら、どうぞ」
「あまりからかわないで頂きたい。……彼女は見ての通り、滅びに侵されている。どうか
貴女の業で救ってはもらえまいか」
すっ、とシスターの眼が焦点を失い細められる。
「――蜘蛛の気配。分かりました、他ならぬ貴方の頼みとあらば事情はあえて聞きますま
い。彼女のことはお任せください」
「お願いする。もう一つ、こちらが本題なのだが……葦原学院の校舎を一部改修するため
に、建材の搬入が必要になった」
「ふふ。それが、開門するための口実かしら? いいでしょう、それも手配しておきます。
ところで、貴方がこうしてここにいるということは、例の事件は解決したのでしょう
ね?」
「……ええ。食人鬼は妖蜘蛛の変異であり、すでに我が使い魔に飲まれて滅び申した」
しばし、礼拝堂は冷たい沈黙に包まれる。
静寂を破ったのは、シスターだった。
「ふふ……あはは。そう――ですか。食人鬼は蜘蛛の変異、だったのですね」
「そういうことです。何か、疑問でも?」
「いいえ、何も。疑問の余地など何一つありません。ただ、貴方が相変わらず、砂糖菓子
のような御方だということが分かっただけ」
くすくすと含み笑う。
「心外ですな。闇遣いの獅条恭二といえば、冷酷非道で通っているのですが」
恭二の顔は先ほどから、ずっと変わらぬ凶相を保っている。容貌だけを見るならば、彼
に慈悲の欠片も見て取ることはできまい。
「えぇ、そうでしょうとも。ですから言い換えます、貴方はまるで――砂糖を入れすぎた
アイスコーヒーのよう。そうやって、甘さを黒さで覆い隠している」
シスターは静かに両目を閉じる。何もかもを包み込む、聖母のような表情だった。
「今日はもうお休みなさい。教会の地下ならば、貴方が厭う太陽の光も届きません。
胸の傷も、尽きた妖力も……癒されるまでいてくれていいのですよ」
「……では、お言葉に甘えて。一晩だけお世話になりましょう。
どうやら、よくよく貴女に隠し事はできぬようだ。この傷は、つい先程弟にやられたも
のでしてね。いや、あれも知らぬうちに強くなった」
呟く恭二の口調は、嬉しそうだった。
祭壇の横を通り抜け、扉に手をかけた恭二へと声がかかる。
「せっかくですから。一晩と言わず、しばらく逗留していっては如何かしら」
「そういうわけにもいきますまい。大事な用件を仰せ付かっておりますので」
「あら、どんな?」
恭二は扉を開けて振り返り、一言で答えた。
「……メモリーカードを買って帰らねば」
*
夜が明けて、昼が過ぎ……再び日が沈んだ頃。恭二は教会を辞していった。
『門』はようやく安定期に入り、あれほど荒れていた夜空は静かに凪いでいる。
再び世界が隔絶されるまでには、あと一週間ほどかかるだろう。
それまで悪意あるものから『門』を守り、恭二から承った建材の搬入という仕事をこな
さなければならなかった。
どちらも有能な部下に一任しておいたので大事はない。
シスター自ら臨まねばならない仕事は、一つだけ。
それも先ほど一区切りつき。今、シスターは祭壇の上に横臥する少女の姿を眺めている。
人形のように整った白皙。
長い瞼がぴくりと動き、やがてゆっくりと瞼が開いていく……。
「気が付きましたか?」
「……ぇ……ぁ……」
少女は戸惑ったように、瞬きを繰り返した。
「大丈夫、ここは安全よ。貴方を脅かすようなものは何も、ここにはいません。
どうか安心してくださいな」
優しく、そして不思議と説得力のある言葉は、少女の心を落ち着かせたようだった。
「私は、シスター・ミナギ。シスターと呼んでください」
「……私は……」
シスターは少女の頬を撫でる。
「思い出せなくても、いいのよ。貴方は記憶を失っているの……しばらく、ここが自分の
家だと思って頂戴」
しばらく俯いて黙していた少女は、儚い声で「はい」と頷いた。
「いい子ね」
シスターは手を差し伸べ、少女の手をとって立ち上がらせると、
「少し待っていて、お風呂の準備をしてきますから」
そう言い残して、奥へ入っていった。
*
シスターはそう言って、奥の扉へと入っていった。
胡乱な顔でそれを見送った少女はふらふらと夢遊病患者のように足を運んで、外に至る
扉を開いた。吹き込む微風が、夜の匂いを運んでくる。
見覚えのない景色――いや。
元より自分にはもう、見覚えのある景色などありはしないのだ。
「私……どうして生きてるの?」
黒い蛇に飲み込まれた記憶を思い返し、少女は身震いした。
あれは断じて悪夢などではなかった。あの恐怖が虚構だったなど、とても信じられない。
けれど……それではアレは何だったのか。幾ら自問しても答えは出なかった。
……あの怖い男の人は、どこへ行ったのだろう?
そして罪を犯したという以前の自分は、どこへ行ってしまったのか?
思い出せない。記憶のない自分には、何も分からない。事態にただ、流されるばかり。
少女は教会の入り口から夜空を見上げる。以前の自分も、かつてこうして空を眺めたこ
とがあったのだろうか。
雲一つない空には、僅かに欠けた月が孤独に浮かんでいる。
どうしてだろう……たったそれだけのことが、酷く不思議な光景のように思えた。
「何を見ているの?」
後ろから、優しい声がかけられる。
「月が……
シスターはくすくすと笑って、少女の肩に手を乗せた。
「あたりまえでしょう? 月はずっと昔から、黄金色に光っているものなのですから」
*
それから、幾日かが経った。
「私は町までお買い物に行ってきます。陽香さん、外を掃いておいて頂けるかしら。
それとお部屋の掃除もお願いね」
「はい、シスター」
返事をして、シスターを見送る。さっそく物置から箒を取り出して掃除を始めた。
何もすることがないので、せめて雑事の手伝いなどをさせてもらっているのだ。
外に出たのは病院に行った一度きり――それも夜間だったので、扉を開けるまでに少し
だけ躊躇してしまった。
相変わらず記憶は戻らない。ただ――深雲陽香、それが自分の名前なのだという。
試しに紙に何度か書いてみると、それが間違いないことが分かった。
他のどの文字よりも、しっくりと手に馴染む書き心地。心が忘れても、何度となく書き
連ねた自分の名前を、指先は確かに覚えていたのである。
病院の医師によると、脳波に異常は見られなかったので、頭部に衝撃を受けたことによ
る一時的な記憶喪失ではないかと言うのだが……陽香には、もう二度と喪った記憶が戻っ
てくることはないのだという、根拠のない確信があった。
ただ普通の記憶障害と異なるところは、通常喪われる筈のない一般常識まで、欠落して
いる部分があるという点だった。
黄金色に光る月なんて、陽香は知らない。
煌びやかに光る街の明かり、夜を昼に変える電灯なんて、陽香は知らない。
生まれ育った筈の国は、記憶をなくした陽香にとって見知らぬ異世界に変わっていた。
異世界――そうだろう。だって陽香にはこの国の名前すらも思い出せなかったのだから。
怖かった。
自分を取り巻く世界の何もかもが怖かった。
いや、一番怖かったものは、何者なのかも分からない自分自身であったかもしれない。
圧倒的な孤独感が、陽香の心に根付いていた。
事情を聞くところによると。陽香が海の傍で倒れているところを、この教会の神父さま
が見つけて、助けてくれたらしい。
その神父さまは長期の出張中らしく、まだ会ったことはない。
一度意識が戻り、自分の名前を名乗ったのだとシスターは神父さまから聞いたのだそう
だ。けど……そんな記憶はどこにも残っていなかった。陽香の最初の記憶は、あの黒い男
の人で始まっている。
あの人は、何も思い出せないのは罰なのだと言っていた。
なら、思い出すべきではないのかもしれない。
思い出してはいけないことなのかもしれない。
生まれ変わったのだと思いなさい。そうシスターは励ましてくれた。
だけど生まれたばかりの陽香には生きる目的というものがない。
以前の自分が持っていただろう生きるための意思が、根こそぎ喪われてしまっている。
心の中に、大きな空洞がぽっかりと空いていた。かつてそこにあった筈の大切なものが、
今はもう何であったのかも思い出せない。
自分はこの見知らぬ世界で、これから何のために生きていけばいいのだろう。
手を動かしながら、延々と纏まらない思索にふけっていた陽香は、いつの間にか教会の
裏手まで来てしまっていた。
この先は絶壁になっているので危ないと注意されたことを思い出す。
いっそ、ここから身を投げてしまえば思い悩むこともなくなるのかもしれない。
記憶が入っていた瓶の底に、未だ残留している罪悪感と寂寥が、陽香の心に囁きかける。
一歩踏み出し、顔を上げる。すると――。
それだけで負の想念は、纏めて吹き飛ばされてしまった。
海。
目の前には海があった。
見渡す視野は、どこまでも深い青を湛えた海原が広がっている。
海――初めて見たということはない筈だ。
でも、陽香が知っている海はこんなものではなく、命の育たない濁った灰色の水溜りだ。
あれは、どこで見た景色だったのだろうか。
今、確かにここにある海は、夏の陽光を水面に照り返し、眼を開けていられないほどに
眩く煌いている。
「綺麗……」
それは生命の輝きだ。なんて壮大で、素晴らしい光景なんだろうか。潮の薫りは清々し
く、吸い込む空気さえもが美味だった。
陽香は掃除の手を止めていることさえ意識の外に追いやって、唯々……いつまでも魅入
られるように立ち尽くしていた。
どのくらいそうしていたのか……気付けば陽香は駆け出していた。
もう思い出せない約束があった。
もう思い出せない面影があった。
もう思い出せない出逢いがあった。
もう思い出せない別れがあった。
どれ一つとして、今の陽香には思い出すことができない。
なのに彼女は何かに突き動かされるように、砂浜に向かって走っていく。
その先には少年がいた。学生服を着た、白い髪の見知らぬ少年が。
彼は走ってきた陽香を見るや、驚いて三白眼を見開き……そして気を取り直して笑った。
白い歯をむき出しにした、悪餓鬼のような笑顔で。
そして彼は、何を言うべきかも分からず汗まみれになって肩で息をする陽香に向かって、
こんなことを言ったのだった。
「初めまして、俺は獅条七夕というもんだ。あんたは?」
「――――」
見覚えは確かにあるのに、陽香には彼のことを思い出すことができなかった。
思い出すことが出来ないのに涙が出た。
思い出すことが出来なくて涙が出た。
「初めまして……獅条くん。私は……陽香……深雲、陽香といいます」
いきなり泣き出した陽香のことを、彼は変な女だと思っただろうか。
見ると……眼に塵でも入ったのだろう、彼は掌で眼を擦っていた。
「七夕でいいよ。なぁ、陽香さん。あんたも日没を見に来たんだろう」
「えっ?」
「違うのか? ここは絶景なんだってよ。ほら――」
彼に導かれるままに海を見ると、丁度右手の山陰に、日が沈むところだった。
雄大な霊峰に落ちていく太陽。
一日の終わりを象徴するかのような光景は、どこまでも美しく幽寂だ。
暮れなずむ空。黄昏に染められて、海が燃えるように赤く輝いていた。
水平線は遠く、世界の彼方まで続いている。
この世界に果てはなく、天も地も、限りなく広がっている……そう思い知らされる。
今ならば確信できる。陽香はここではない別の世界からやって来たのだと。
大気は清らかに澄み渡り、そよぐ風はどこか優しい。世界に意志があるのなら、この大
地は何もかもを包み込むような母性に溢れているのだろう。
「陽香さん、かぁ……いいですね、その響き。でも七夕くん、『さん』はいらないかな」
「……分かったよ、陽香。これでいいか?」
「はい、よろしい」
横目に窺うと、彼は魂を抜かれたように放心して、落日に魅入っている。
そのまま……日が落ち切って暗くなるまで、二人並んで海を眺めていた。
「さて。用は済んだし、俺はもう帰るよ」
「うん……また、会えますか?」
あまりに名残惜しかったのでそう聞くと、彼は困ったような顔をした。
「どうだろうな。実は俺、すごく遠いところから来たんだ。次にいつ来られるかは分から
ない。……だけど、次はあんたに会いに来るのもいいかもしれない。
こうして会ったのも何かの縁だ。折角だから、友達になろうぜ」
そのフレーズは、いつかどこかで聞いたような――懐かしい響きがした。
「はい……! では、またいずれ」
「ああ――またな、陽香」
彼は片手を軽く挙げて、また明日会えるかのような気安い挨拶をしてくれた。
もう暗い砂浜を、彼はしっかりとした足取りで歩いていく。海に向かって何事か呼びか
けると、海で遊んでいたのだろう人影が彼の側に走り寄った。
そうして二人は仲良く、ふざけ合いながらどこか遠い場所へと帰っていった。
羨ましくて、遠い光景。
喪ってしまったものの中にも、あんな――輝くような想い出があったのだろうか。
「うん」
おかげで一つ目標ができた。
なくしたものが帰ってこないのなら、何度だって作ればいい。
胸に空いてしまった穴は元通りになることはないけれど。
これから頑張って、かつての自分に負けないくらい、多くのものを詰め込んでいこう。
いつの日か、また彼に会った時に、自分のことを沢山話して聞かせられるように。
この想いがあれば、それだけで十分に、深雲陽香は生きていける。
まずは、一つ。
最初の想い出は、真新しいアルバムの頁に挟まれて、大切にしまわれていった。
真夏の海辺、二人で夕焼けを眺めた日のこと。
あやかしの夏 了
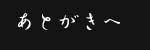
■Web拍手ボタン■